山本孝史のプロフィール
誕生から大学卒業まで
1949年(昭和24年)
- 7月7日

父愛用のカメラで4歳の誕生日に - 11月
- 空襲で大阪市内中心部は焼け野原となったが、父、隆一(たかいち)の経営する「エビスはぶらし」(大阪市東区南久宝寺町)の店舗再建、そして近隣の大阪市南区順慶町1丁目(じゅんけまち=現大阪市中央区南船場)に自宅が完成し、芦屋から転居。敗戦から4年。ようやく疎開生活が終わった。
1955年(昭和30年)
- 2月2日

兄に負けじと張り合う私 戦後、順慶町周辺は住宅街から様変わりし、自宅は両隣を運送業者に挟まれる格好になっていた。父は不運を嘆き、危険と隣り合わせの場所に自宅を構えていた優柔不断さを責めた。母の英子(えいこ)が亡骸となった兄の脚をさすっていたこと、毎晩、御詠歌をあげていた姿は今も鮮明に覚えている。
1956年(昭和31年)
- 3月
- 桃園幼稚園(大阪市中央区)卒園。夏に罹った百日咳で、学芸会での「小さな靴屋さん」のナレーター役ができず残念。せっかく父親が購入したテープレコーダーで練習したのに。在籍日数も足らず、卒園式では後ろに座っていた。
- 4月
- 大阪市立集英小学校(児童数減少のため統合され、現在は開平小学校)に入学。杉田貞三校長先生、担任の水本多加嗣先生には、選挙区にお住まいだったこともあって、国会議員になった後もお世話になった。
1962年(昭和37年)
- 4月
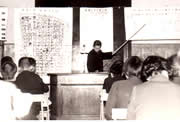
足で歩いて地域を調査し、一生懸命に発表する私
1963年(昭和38年)
- 11月23日
- 父の仕事の関係で、はぶらしの全国的な産地である府下八尾市刑部に転居。初の国際衛星放送の日だった。ケネディ暗殺のニュースが流れていた。
1965年(昭和40年)
- 4月
- 立命館大学産業社会学部入学
- 7月
- 中学生の時に味わったキャンプの楽しさを後輩にもとの想いから、京都YMCAの琵琶湖サバエキャンプ場でのキャンプカウンセラーに応募。夏休み中、日焼けしながら、お兄さん役を担う。
1970年(昭和45年)
- 3月
- 大阪万博開催。身体障害者の介助ボランティアに応募。これがきっかけとなって、大阪ボランティア協会(当時は大阪市南区心斎橋)のボランティアスクールを受講。
- 8月
 この大阪ボランティア協会で、全国学生交通遺児育英募金を呼びかけていた秋田大学生の生路さんと運命の出会い。交通遺児作文集「天国にいるお父さま」(写真)に感涙。夭折した兄の無念さや、両親の悲しみが一気に胸にあふれた。
この大阪ボランティア協会で、全国学生交通遺児育英募金を呼びかけていた秋田大学生の生路さんと運命の出会い。交通遺児作文集「天国にいるお父さま」(写真)に感涙。夭折した兄の無念さや、両親の悲しみが一気に胸にあふれた。
募金活動の手伝いを頼まれ、10月の交通安全旬間の10日間、梅田花月前で街頭募金に立った。
10月に、なぜか募金の贈呈式に参加して欲しいとの連絡があり、上京。永野重雄交通遺児育英会会長(日本商工会議所会頭)への贈呈式に列席。玉井義臣氏と運命の出会いをした。- 12月
 募金参加者に呼びかけて、ボランティアグループ「大阪交通遺児を励ます会」を結成。
募金参加者に呼びかけて、ボランティアグループ「大阪交通遺児を励ます会」を結成。
飯野俊男君という得がたい仲間を得て、交通遺児と母親の作文集「おとうちゃんをかえせ」(写真)の発刊、レクリエーション、交通遺児家庭の生活実態調査、政治への要望の会などの活動を展開。市民活動の芽生えでもあった。
1971年(昭和46年)
- 4月

大会参加者と銀座をデモ行進。
左端が私全国に交通遺児を励ます会の結成を呼びかけ、励ます会全国協議会の事務局長に就任。
12月には、第1回の交通遺児と母親の全国大会を開催した。
